MIDGET TOSSING
1997年。

WHERE WE STAND
1999年。バイオリン奏者、ギター2人を含む6人編成。ドラムはアフリカ系、他の5人は白人。アメリカ出身。ハードコアにバイオリンとメロディアスなボーカルが乗っているが、勢いに任せた演奏でアンサンブルのまとまりにはやや欠ける。

ONE FOR THE KIDS
2001年。ボーカル、ギターが抜け、ボーカル兼ギターが加入。5人編成。ハードコアではなく、エモ、あるいはメロディック・パンクとなっている。ボーカルメロディーも追いやすく、アコースティック・ギターも使用する。バイオリンがボーカルを兼任するので、ロックの世界ではカンサスのロビー・スタインハートが思い出される。彼よりは歌い上げるボーカルで、なじみやすい。
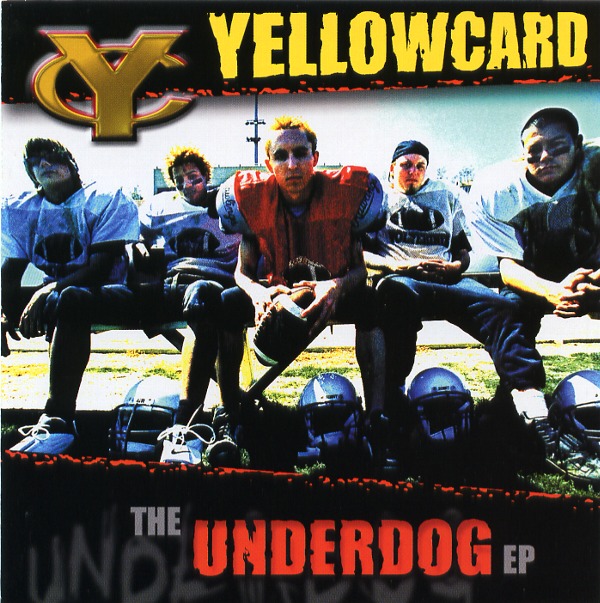
THE UNDERDOG EP
2002年。5曲入りEP。これまで以上にバイオリンが多用されている。「エイボンデイル」の最後はメタルコアのような絶叫型ボーカルが出てくる。

OCEAN AVENUE
2003年。ベースが抜け4人編成。ベースはゲスト・ミュージシャンが演奏している。「ワン・フォー・ザ・キッズ」の路線を継承。バイオリンに注目が集まる上にメロディアスで、インパクトは大きい。バイオリンがなくても通用するロック。このアルバムで日本デビュー。全米23位。

LIGHTS AND SOUNDS
2006年。ベースが復帰、ギターが交代。5人編成。このアルバムではボーカル兼ギターがベースも弾き、新たに加入したギターは演奏していない。バイオリンが前作ほどメロディーを主導せず、音の大きさを含めても後方に引っ込んでいる。曲によってはオーケストラ並みのストリングスが入る。「ウェイティング・ゲーム」はもともとがパンクのバンドとは思えないほど壮大だ。最後の曲には女性ボーカルも入る。全米5位。

PAPER WALLS
2007年。ギターが交代。前作の揺り戻しか、大手レコード会社に移ってから発売された「オーシャン・アヴェニュー」以降最もハードだ。オープニング曲の「ザ・テイクダウン」は、このバンドがもともとどんなサウンドだったかを再認識させる曲。このバンドの特徴はもちろんバイオリンが入っていることであるが、バイオリンがなくても曲の良さやサウンドの厚さだけで他のバンド群に対抗できる。覚えやすいメロディーが多い。「ディア・ボビー」はピアノとバイオリンとアコースティック・ギター中心のバラード。全米13位。

WHEN YOU'RE THROUGH THINKING,SAY YES
2011年。ベースが交代。「オーシャン・アヴェニュー」のころの雰囲気に戻った。バイオリンがギター並みに活躍し、ハードさとメロディアスさがほどよく同居している。曲もよく、バイオリンがなくてもメロディーだけで戦える。復活と言っていいだろう。このアルバムから大手レコード会社を離れ、非大手から出ている。全米19位。

SOUTHERN AIR
2012年。ベースが交代。前作に続き、古いLPレコードを模した、円形の色あせのあるジャケットとなっている。懐かしさを出す戦略か、サウンドもメロディアスで半音階がよく使われる。「オールウェイズ・サマー」は流麗なバイオリンソロが入る。「リヴァータウン・ブルース」は高速演奏。全米10位。
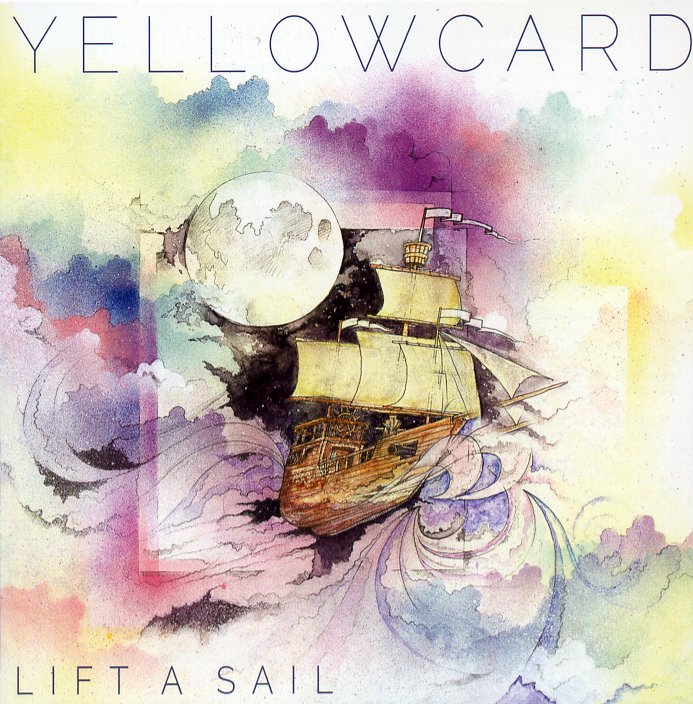
LIFT A SAIL
2014年。ドラムが抜け4人編成。バイオリンの活躍が大幅に減り、エレクトロニクスがやや増えた。バイオリンが出てくるのは「コンヴォケーション」「フラジャイル・アンド・ディア」「MSK」くらいで、他の曲は背景音として薄く出てくるか、全く出てこない。「ライツ・アンド・サウンズ」以来のバイオリンの少なさは、このバンドの迷いを反映していると言えるだろう。バイオリンによる情緒性と古風な響きはエレクトロニクスの新進性と背反ではない。サウンドそのものよりも、バイオリン奏者がいることを生かさずに別のサウンドを目指す姿勢が不審を招くのではないか。アルバムのサウンドは、結果的にイエローカードがやる必然性を失っているものの、質が落ちていいるわけではない。全米26位。

YELLOWCARD
2016年。解散することを前もって宣言した上で発表されたアルバム。イエローカードは、バイオリンを前面に出したロックではなく、バイオリン奏者もいるロックに軸足を置いたことが、物足りなさをを生んでいたのではないか。また、カントリー系のフィドルなのかクラシック系のバイオリンなのかについても曖昧で、バンド側もバイオリンの取り扱いに迷いがあった。これまでのアルバムは、バイオリンの有無を超えた普遍的なロックを目指そうとした軌跡だったと感じられ、それはこのアルバムでも続いている。最後だからといって特にバイオリンが活躍するわけではないが、エンディング曲の「フィールズ&フェンシズ」の最後が弦楽合奏になっているのは、終焉を感じさせる。全米28位。