
VAMPIRE WEEKEND
2008年。邦題「吸血鬼大集合!」。ボーカル兼ギター、ベース、ドラム、キーボードの4人編成。アメリカ、ニューヨーク出身。キーボード、ストリングスが入ったアークティック・モンキーズのようなサウンド。ストリングスはチェロが中心で、バイオリンよりもクラシック風に聞こえる。サウンドはパーティーというほど派手ではなく、アフリカらしいパーカッションも、曲によっては、という印象だ。

CONTRA
2010年。メロディー楽器もリズムを主体にした演奏で、音のひとつひとつが細かく刻まれる。バンド編成だがギターの音は少ない。ドラムを含めた打楽器が多彩で、リズムも単純ではない。音のほとんどを減衰音にしてサウンド全体を涼しくしている。ニューヨークから出てきたバンドにしてはサウンドで聞き手をねじ伏せるところがなく、引き気味であるところが知性を感じさせる。「カズンズ」収録。

MODERN VAMPIRES OF THE CITY
2013年。ボーカルがギターを演奏しなくなり、キーボード奏者がベースとドラム以外の楽器をほぼすべて演奏している。従ってサウンドの主導権はキーボード奏者にある。使われている楽器は古風だが、音の編集、加工の仕方が現代的であるため、懐かしさによる安心を感じながら、古さを感じないサウンドになっている。「アンビリーヴァーズ」「ウォーシップ」は60年代後半の発展途上国の音楽を思わせるアップテンポの曲。「ダイアン・ヤング」はハードなロック。「ドント・ライ」は60年代前半のソウルのようなサウンド。ジャケット写真は1966年にニューヨーク・タイムスに掲載されている写真で、ブックレットはそのことを強調している。バンド側がイメージするサウンドは、1966年ごろの英米の若者にあった漠然とした不安の中の少しの希望であり、それは現在の先進国都市部の若者と同じだ。
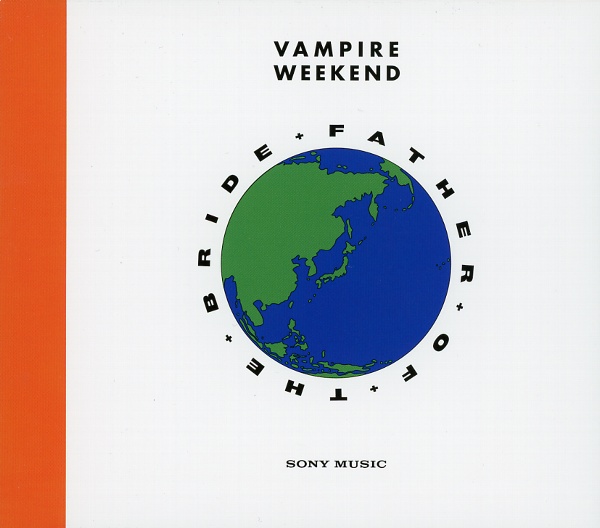
FATHER OF THE BRIDE
2019年。ロスタム・バトマングリが抜け3人編成だが、ギター、キーボード、ギター兼キーボード、パーカッションの4人を一時的に加入させて7人編成となっている。1分半から5分の曲を18曲並べ、以前よりもカントリーポップ、室内楽ポップ寄りになった。短い曲が多く、雰囲気が異なる曲を1枚のアルバムに収録して全体の傾向をあいまいにしている。ヴァンパイア・ウィークエンドのサウンドを特徴づけていた非欧米感は、ロスタム・バトマングリがかなりの部分を担っていたということが分かる。次作は重要になるだろう。ジャケットの世界地図は発売地域によって異なっている。

ONLY GOD WAS ABOVE US
2024年。1曲目からヴァンパイア・ウィークエンド特有の編曲が効果的に出てくる。バンドともにオーケストラも参加するが、「カプリコーン」「ジェン・X・コップス」など、適度に不協和音を残す。その不協和音や雑音が弦楽四重奏が入る「プレップ・スクール・ギャングスターズ」はバイオリンの弾き方が現代的だ。「コネクト」はニューヨークの猥雑さと冷気と前衛性を併せ持ったようなジャズ寄りの曲調。アルバム全体の統一性もよく、デビュー以来の最高作と言ってよい。