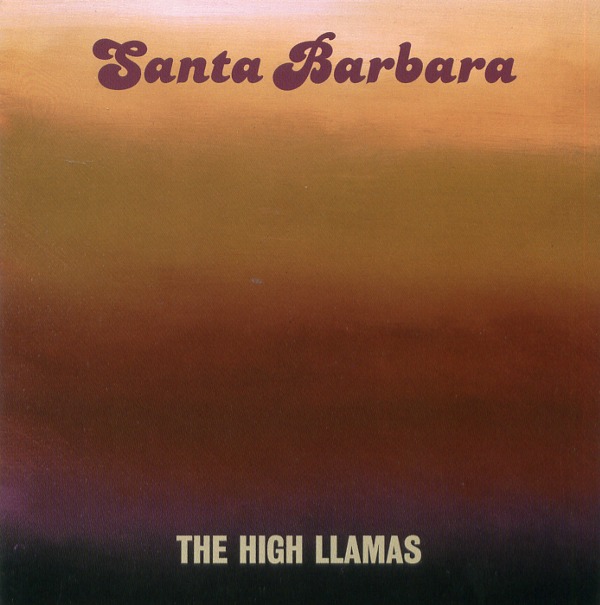
SANTA BARBARA
1992年。ボーカル兼ギター兼キーボードのショーン・オヘイガンを中心とするバンド。ギター兼ボーカルの女性、ベース、キーボード、ドラムの5人編成。ドラムは曲によって2人が分担している。1970年代前半のアメリカ、カリフォルニアのフォークロックに似たサウンドで、オープニング曲はアルバート・ハモンドの「カリフォルニアの青い空」を思い出す。コーラスもアメリカ風で、女性ボーカルがいるところがいい。ストリングスも使う。日本盤は1998年発売。

GIDEON GAYE
1994年。ギター、ピアノ、シンセサイザーなど、(エレクトロニクスやリズム・マシーンではない)従来型の楽器を使いながら、やや器楽的な曲を演奏する。ポップな曲にしようと思えばできるが、意図的にしなかったような雰囲気がある。インスト曲が半数あり、1分以下の曲も複数ある。「トラック・ゴーズ・バイ」は14分。「ザ・ゴート(インストゥルメンタル)」は歌詞があり、インスト曲ではない。日本盤は1995年発売。このアルバムで日本デビュー。
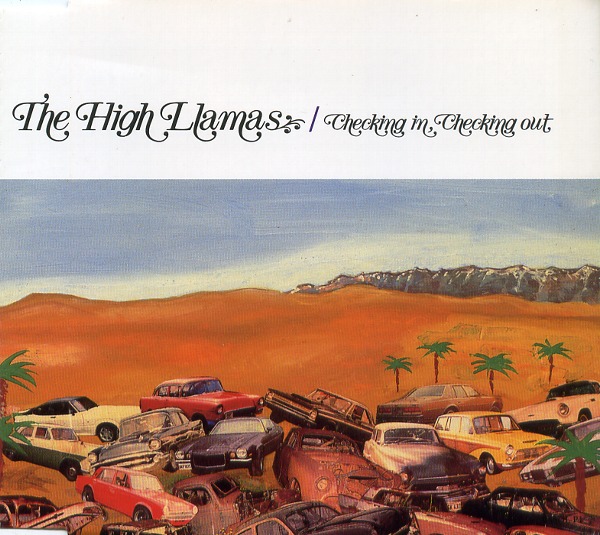
CHECKING IN,CHECKING OUT
1994年。シングル盤。「アプリコッツ」「クロップダスター」はアルバム未収録曲。「クロップダスター」はショーン・オヘイガンのバンジョーとビブラフォン、ハープシコードがメーン。

HAWAII
1996年。29曲あり、10曲が1分以下。12曲は歌詞があり、17曲はインスト曲。ピアノ、シンセサイザー、ビブラフォン、ストリングスがアルバム全体を柔らかくしている。60年代から70年代初頭のソフトロックを難しく、またはサイケデリックにしたサウンド。実験的であろうとする姿勢はうかがえるが、独創的かどうかは判断がわかれる。

LOLLO ROSSO
1998年。ハイ・ラマズの曲を7組のアーティストがリミックスした企画盤。コーネリアス、ジム・オルーク、キッド・ロコ等がリミックスしている。「ミルティング・ティンドミルズ」はハイ・ラマズによるリミックス。

COLD AND BOUNCY
1998年。16曲のうち、ボーカル入りが7曲、インスト曲が9曲。ボーカルのあるなしにかかわらず、4分から6分の曲が多い。従来のバンドサウンド、ストリングス、ホーンセクションを中心にして、跳ねるようなエレクトロニクスを多用している。メンバーにDJがいても不思議ではないサウンドだ。

SNOWBUG
1999年。前作の反動なのか、再び楽器演奏のサウンドに戻った。エレクトロニクスも少し使われているが前作ほど多くない。明るいポップスではなくリラックスしたポップスで、そうした雰囲気を作っているのはビブラフォンやマリンバだ。女性ボーカルはステレオラブの女性2人。「グリーン・コースター」のイントロはスティーヴィー・ワンダーの「迷信」を思い出す。

BUZZLE BEE
2000年。ボーカルがある曲とない曲が交互に出てくる。ステレオラブの女性ボーカルが参加しているため、ボーカルは男女2人いる。ギターの使い方がどの曲も似ており、メロディー楽器としての機能は少ない。ステレオラブと同じく、木琴、ビブラフォンがよく使われる。「ゲット・イントゥ・ザ・ギャリー・ショップ」はポップだ。
RETROSPECTIVE RARITIES AND INSTRUMENTALS
2003年。ベスト盤。

BEET MAIZE&CORN
2003年。ほとんどの曲をストリングスとホーンセクション、ピアノ、パーカッションで演奏し、ドラムやエレキギターはほとんど出てこない。クラシックで言えば室内楽の編成に管楽器が加わっているサウンドだ。今回はショーン・オヘイガンが12曲のうち10曲でボーカルをとっている。アルバムごとにサウンドが変わっているが、穏やかで角の立たないポップスという雰囲気は一貫している。
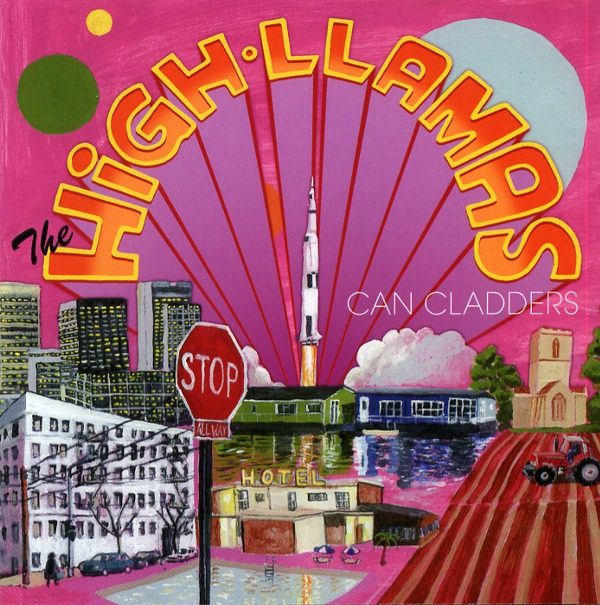
CAN CLADDERS
2007年。60年代のソフトロックのサウンド。ストリングス、ピアノ、女性ボーカルが入る。60年代のサウンドを今再現するというのが狙いであるならば、高く評価されないのが妥当だと言える。当時一般的ではなかったビブラフォン奏者がメンバーにいることは、サウンドの質感や感触を決定するという意味で新しいのかもしれない。
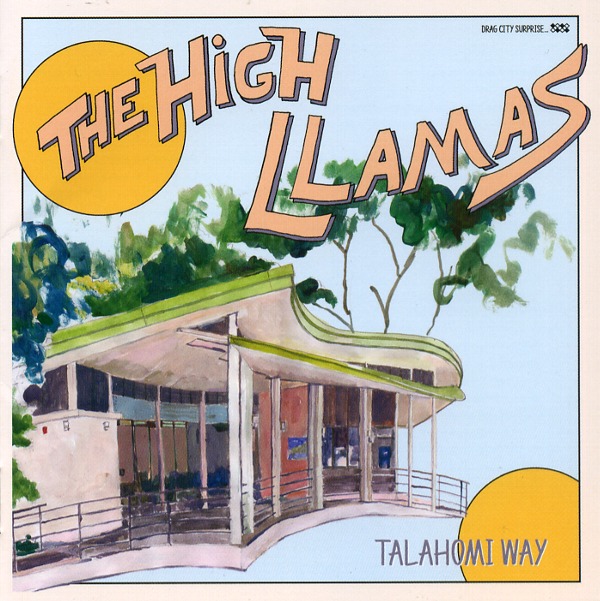
TALAHOMI WAY
2011年。前作と同様のサウンド。驚きではなく安心を重視する姿勢のため、従来のファンやソフトロックのファンには評価されるだろう。