
WHEN DREAM AND DAY UNITE
1989年。キーボードを含む5人編成。アメリカ出身。このアルバムの登場はプログレッシブ・ロックとヘビーメタルの両方を聞く人にとって相当の衝撃だった。めまぐるしく変化するリズムは、イエスがヘビーメタルをやっているようにも聞こえた。ボーカルの線の細さと音質の悪さをかき消してしまう革新性があった。プログレッシブ・ロックの音像をヘビーメタルに導入しようとする試みは過去にもあったが、キーボードでシンフォニックにしすぎたり、テンポを遅くしすぎたりしてヘビーメタルの攻撃性を失うことが多かった。そうした失敗の多くは曲進行の主導権をキーボードが握ってしまうことが原因だったが、このアルバムでは、あくまでギターとドラムが中心だ。「オンリー・ア・マター・オブ・タイム」「アフターライフ」収録。

IMAGES AND WORDS
1992年。ボーカルが交代し、ジェイムス・ラブリエが加入。大ヒットし、プログレッシブ・ヘビーメタルというジャンルを創出、開拓した金字塔的作品。ボーカルの力量、音質も圧倒的に向上した。ライブではギターとキーボードがまったく同じタイミングでユニゾンを決め、このスタジオ盤ではわざと音をずらしてレコーディングをしているのではないかという噂されるほどだった。「メトロポリス」「プル・ミー・アンダー」「アナザー・デイ」「アンダー・ア・グラス・ムーン」収録。

LIVE AT THE MARQUEE
1993年。ライブ盤。海外盤と日本盤は収録曲が違う。日本盤は「アナザー・デイ」の代わりに「サラウンデッド」が入っている。海外盤にはバンドからファンに対するメッセージも掲載されているが、それも外されている。前作のジャケットにも登場している「燃える心臓」はクレイドル・オブ・フィルスのベスト盤にも描かれているが、「燃えさかる情熱(信仰心)」の意味で昔の絵画作品にも頻繁に出てくる。有刺鉄線は様々なしがらみを表している。「ボンベイ・ヴィンダルー」はインスト曲。ベースが聞こえにくい。

AWAKE
1994年。ギターの音の歪み具合が大きくなり、「冷たくなった」と評された。サビのメロディーが下降になって重さを強調した曲もある。「リフティング・シャドウズ・オフ・ア・ドリーム」は前作路線。「ザ・サイレント・マン」は初の本格的アコースティック作品。全体的にもの悲しく陰鬱で、時代の空気を読みとった音という意味では、ロック作品として出色の出来だ。日本盤の初回盤にはシングルCDがついていた。「イノセンス・フェイデッド」収録。
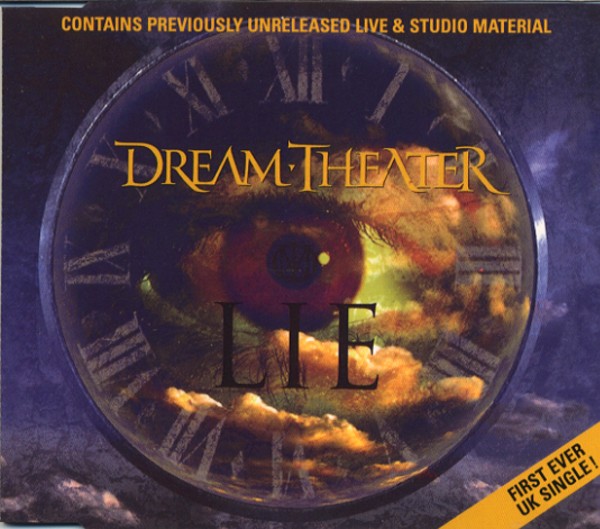
LIE
1994年。シングル・タイトル曲のエディット・バージョンのほか未発表曲1曲。アルバムに入っていてもよかった。

THE SILENT MAN
1994年。「テイク・ザ・タイム」のデモ・バージョンと日本盤初回盤についていたシングルの「イヴ」を収録。

A CHANGE OF SEASONS
1995年。キーボードのケヴィン・ムーアが脱退し、デレク・シェリニアンが加入。タイトル曲は23分を超える長大な曲。「葬送・血まみれの恋はおしまい」はエルトン・ジョン、「パーフェクト・ストレンジャーズ」はディープ・パープル、「流浪の民・アキレス最後の戦い・永遠の詩」はレッド・ツェッペリンのカバー。「ザ・ビッグ・メドレー」はピンク・フロイド、カンサス、クイーン、ジャーニー、ディキシー・ドレッグス、ジェネシスのカバーのメドレー。カバーされたアーティストのうち、ディープ・パープルやレッド・ツェッペリンは面白みがない。エルトン・ジョンは、傑作「黄昏のレンガ路」からプログレッシブ・ロック的な曲を選曲してファンをうならせた。「ザ・ビッグ・メドレー」はアメリカ人らしい選曲。このアルバムに伴うライブではイエスの「燃える朝やけ」をやっていた。カバーはすべてライブ・バージョン。

FALLING INTO INFINITY
1997年。ミドル・テンポが多くなり、曲の途中でリズムがめまぐるしく変わることは少なくなった。淡々と進行する。ピンク・フロイドのような印象。ジェイムス・ラブリエが声を張り上げて歌うこともなく、これをヘビーメタルと呼ぶにはおとなしい感じがする。ハードロック、さらにはもっと一般的なロックといってもよい。「ホロウ・イヤーズ」収録。

HORROW YEARS
1997年。シングル盤。6曲収録。「ザ・ウェイ・イット・ユーズド・トゥ・ビー」はアルバム未収録曲。「アナザー・ハンド/キリング・ハンド」はメドレー。ライブの2曲だけで22分近くある。

ONCE IN A LIVETIME
1998年。「ライヴ・アット・ザ・マーキー」はシングル扱いなので、このアルバムが初のライブ・アルバム。主な曲はだいたいやっている。レーナード・スキナードの「フリー・バード」、レッド・ツェッペリンの「モビー・ディック」、ピンク・フロイドの「葉巻はいかが」、メタリカの「クリーピング・デス」「エンター・サンドマン」、リムスキー・コルサコフの「熊蜂の飛行」のフレーズを使用。2枚組で2時間半くらいある。即興でどういう演奏をするかが聞き所になるだろう。

METROPOLIS PT.2:SCENES FROM A MEMORY
1999年。キーボードがデレク・シェリニアンからジョーダン・ルーデスに交代。「イメージズ・アンド・ワーズ」の「メトロポリス」の続編。もともと「メトロポリス」には「Part1」というタイトルがついていた。したがって、「パート2」があることはあらかじめ推測できた。このアルバムは、そのパート2を第1幕と第2幕に分け、劇場仕立てにしている。「メトロポリス」のフレーズを随所に使用。前作よりはハード、アグレッシブで、メロディーも起伏に富んでいる。物語の進行とサウンドの相関性は十分練られている。こうしたロック・オペラは筋書きを知るとさらに面白くなる。一般にこの作品のテーマは「輪廻転生」とされている。しかし、「輪廻転生」の思想は、仏教には存在してもキリスト教には存在しない。存在しないからといって、そうした考え方をしないということではないが、ドリーム・シアターのメンバーはアメリカ人であり、当然キリスト教の考え方を通してこの作品の筋書きを考えたはずだ。歌詞を読むと、どうもこの作品のテーマは「輪廻転生」とは別のところにあるようだ。歌詞を読んで、「テーマは輪廻転生だ」と結論づけるのは、間違いとは言えないまでも、本質を突いているとは思えない。
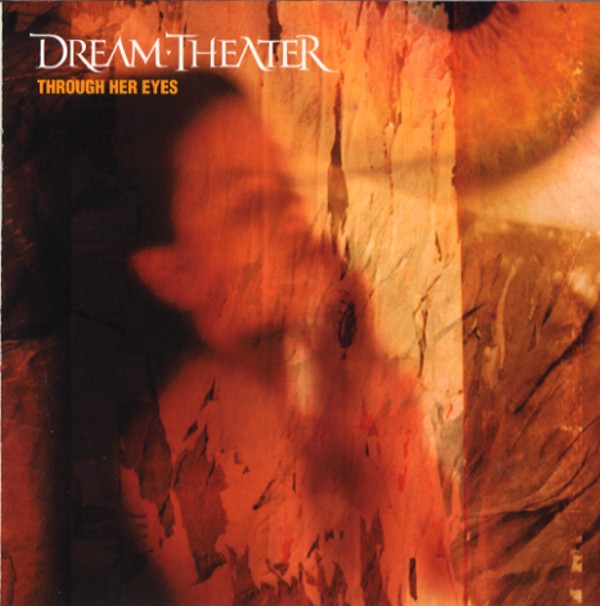
THROUGH HER EYES
2000年。5曲すべてが未発表バージョン等のシングル。「ホエン・ドリーム・アンド・デイ・ユナイト」と「イメージズ・アンド・ワーズ」の5曲をメドレーで演奏するライブが聞きどころ。「オンリー・ア・マター・オブ・タイム」をやっているのは特筆もの。

LIVE SCENES FROM NEW YORK
2001年。ライブを発表するごとに枚数が増え、今回は3枚組。全25曲のうち、1枚目の10曲と2枚目の3曲目までは「メトロポリス・パート2」の再現。残りの12曲は知名度の高い曲。リキッド・テンション・エクスペリメントの曲を1曲やっている。「ラーニング・トゥ・リブ」が途中でレゲエのリズムになる。メンバーの技量が高いのでどの曲もほとんどミスなくこなしている。もはやスタジオ盤の完璧な再現は当たり前で、スタジオ盤からどう変えて演奏しているのかが興味の対象になってくる。前回のライブ盤で分割演奏されていた「ア・チェンジ・オブ・シーズンズ」は完全演奏している。
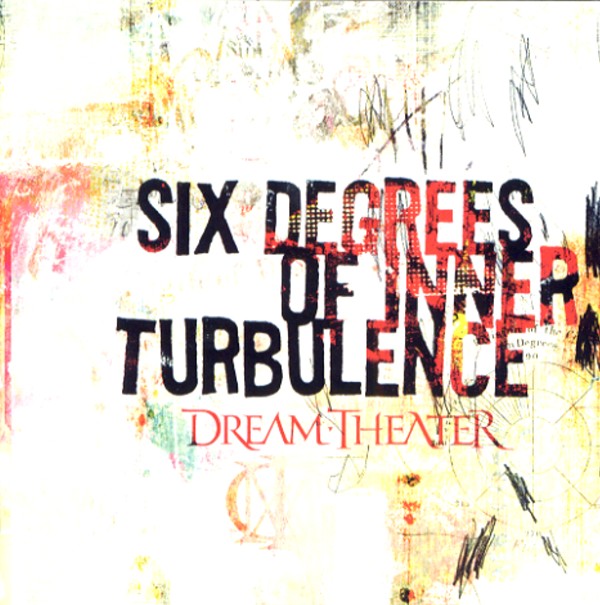
SIX DEGREES OF INNER TURBULENCE
2002年。2枚組。1枚目は5曲、2枚目は1曲とボーナス・トラック1曲。1枚目と2枚目ではっきり音の傾向が異なる。2枚目の1曲は8部構成で42分あるが、これが素晴らしい。明るめの曲調で、ジョーダン・ルーデスの作曲能力が生かされたと思われる。

TRAIN OF THOUGHT
2003年。7曲のうち6曲が10分以上。ジェイムス・ラブリエが歌いあげるというところがほとんどなく、各楽器のアンサンブルと暗めのボーカル、エフェクトをかけたサウンドが目立つ。理解はできなくとも、理解しようとすれば構成にも歌詞にもかなり忍耐力を持って接しなくてはならない。思考を要求するバンド。

LIVE AT BUDOKAN
2004年。3枚組ライブ盤。長大な曲を相当数発表しているにもかかわらず、ライブの各曲のイントロを聞くだけでどのアルバムに入っている曲かがすぐ分かる。そのことに気付いて再びドリーム・シアターのすごさを確認させる。「インストゥルメンタル・メドレー」は過去の代表曲を12分にわたってメドレーで演奏。リキッド・テンション・エクスペリメントの曲もやっている。3時間近くあるのにまったく疲れないどころか、期待を含んだスリルがある。

OCTAVARIUM
2005年。全曲がミドルテンポで、最後の曲は24分、他の曲は4分から10分。ギターよりもキーボードがメロディーを形成し、最近のピアノによるロックの流行に沿っているかのようだ。「オクタヴァリウム」の古風なムーグとオルガンの部分が、他の曲とは異なる雰囲気を持っている。60年代から70年代の有名な曲を歌詞の中に織り込んでいるが、ニール・ヤングの「マイ・マイ、ヘイ・ヘイ(アウト・オブ・ザ・ブルー)」が入っているのがポイント。「マイ・マイ、ヘイ・ヘイ(アウト・オブ・ザ・ブルー)」はニルヴァーナのカート・コバーンが自殺した際に、遺書に引用した曲として有名。ジェイムズ・ラブリエは近年の作品と同じように抑揚を抑えたメロディーを歌う。メロディーも明るくない。そうしたサウンドなり雰囲気なりは、時代の空気を反映しているとも言えるが、ロックン・ロール・リバイバルがブームになったり、エモ、スクリーモが流行したりする2000年代前半にあっては、もう少し激しさや衝動を入れてもよかったのではないか。

SCORE
2006年。3枚組ライブ盤。1枚目はバンドの歴史を追うような選曲のライブ。「レイズ・ザ・ナイフ」は未発表曲。12分近くある。2枚目はオーケストラと共演したライブで、「シックス・ディグリーズ・オブ・インナー・タービュランス」を演奏。ほかに3曲を含めて1時間ある。3枚目は「オクタヴァリウム」と「メトロポリス」の2曲、37分。オーケストラとの共演は、単に共演したというだけのサウンドだ。一般的に高級文化と認識されているクラシックと近付いただけで満足している感がある。メタリカの「S&M」と同じように、ヘビーメタル、ハードロック・バンドに広く見られる、思考停止した保守性が現れている。30、40年前からオーケストラとロックバンドの共演は行われているのだから、なにがしかの新しさが欲しいところだ。

SYSTEMATIC CHAOS
2007年。現在のメンバーになってからは最も聞きやすいアルバムだ。メロディーが明確で、サウンドもそれほど威圧的ではない。キーボードはなじみのあるシンセサイザーの音が多い。最初の曲と最後の曲がパート1、パート2になっている。8曲のうち3曲は10分を超えるが、長くても16分台で、これまでのドリーム・シアターの中ではコンパクトな方だ。プログレッシブ・ロックあるいはプログレッシブ・ヘビーメタルのファンは、長い曲で構成が込み入っていたりすると、そこになにがしかの意味を見つけようとするのが習性になっているが、このようなジャンルが一般の洋楽ファンに全く広がらないのは当たり前だ。一部の真面目なファンを裏切ってでも問題作を作るべきである。ダンス・ミュージックかヒップホップの有名プロデューサーを迎えるのも一つの案だ。

BLACK CLOUDS&SILVER LININGS
2009年。6曲のうち10分以上の曲が4曲あるが、それほど長いと感じさせない。「ザ・カウント・オヴ・タスカニー」はおおむね4部に分割できる。19分の大曲といっても、前奏、ボーカル、ギターソロ、ボーカル部分で曲調が違うだけなので、普通の3分の曲が19分に間延びしただけだ。「ア・ナイトメア・トゥ・リメンバー」は、曲の割には歌詞が単純だ。「ザ・ベスト・オブ・タイムズ」はエルトン・ジョンの「葬送/血まみれの恋はおしまい」に似た雰囲気で、詩の内容からすると、曲のイメージとしてこの曲があったのかもしれない。限定盤は3枚組。2枚目はカバー曲集。レインボーの「スターゲイザー」、クイーンの「シアー・ハート・アタック」の3曲メドレー、ディキシー・ドレッグスの「オデッセイ」、ゼブラの「テイク・ユア・フィンガーズ・フロム・マイ・ヘア」、キング・クリムゾンの「太陽と戦慄パート2」、アイアン・メイデンの「惑星征服」の6曲。「オデッセイ」でバイオリンを弾いているのはフロック、マハヴィシュヌ・オーケストラのジェリー・グッドマン。3枚目は1枚目のインスト版。

A DRAMATIC TURN OF EVENTS
2011年。ドラムがマイク・ポートノイからアナイアレイター等のマイク・マンジーニに交代。エレクトロニクスが一部に挿入されるのと同じ使われ方で古風なシンセサイザーの音も入る。随所に過去の名曲と似たメロディーやフレーズが出てくるため、そのたびに安心感を覚える。ここは、ドリーム・シアターに何を求めるかによって評価が変わるだろう。ジェイムズ・ラブリエのボーカルが抑制されており、「イメージズ・アンド・ワーズ」のように声を張り上げることがない。能力があるのに出さないのは、能力がないのと同じと見られても仕方がないだろう。マイク・マンジーニは個性よりも何でもこなす技術を買われたようで、ドリーム・シアターのサウンド面に何かをもたらすような特異性があまりみられないのは残念だ。個性はなくても作ろうとすれば作れるはずだ。

DREAM THEATER
2013年。自然な流れのメロディーが増え、編曲をもっと簡潔にすれば多くのファンを獲得できそうな曲もあるが、ジョン・ペトルーシがギターを過剰に弾きすぎる傾向がある。マイク・マンジーニのドラムは手数が多く、ヘビーメタルのバンドであることを最も分かりやすく示している。これまでのアルバムは10分以上の曲が複数あるのが普通だったが、今回は22分の「イルミネイション・セオリー」以外は4分から7分台に収まっている。バンド名がアルバムタイトルになっているので、曲調やイメージを変化させるにはいいタイミングだったことを考えると、もっと短くまとめてもよかった。オープニング曲はストリングスを含んだ3分弱のインスト曲。「ザ・ルッキング・グラス」は明るめのなじみやすいメロディーで入るが、後半はいつものリズム転換を入れてしまうため、入り口となるきっかけを逸している。「サレンダー・トゥ・リーズン」は「アロング・フォー・ザ・ライド」は古風なシンセサイザーが刺激を作る。「イルミネイション・セオリー」は5部構成になっており、その中の「ジ・エンブレイシング・サークル」はサラ・ブライトマンの「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」を意識したとみられるメロディーとサウンドだ。「ザ・パースート・オブ・トゥルース」はエマーソン・レイク&パーマーのようなサウンドになる。

THE ASTONISHING
2016年。2枚組で130分ある大作。1枚目を第1幕、2枚目を第2幕と名付けており、アルバム全体がひとつながりの劇、つまりオペラであることを示している。このアルバムは、物語のあらすじよりもアウトラインが重要だ。アウトラインは「音楽の力によって世界に安寧をもたらす」ということだ。少し長く言うなら「理想が失われた世界を、音楽の芸術性そのものによって再び生き返らせ、理想の世界を取り戻す」ということになる。ドリーム・シアターはこれを未来の世界に置き換え、世界をアメリカに限定しているけれども、アウトラインは変わらない。このアウトラインは、1700年代後半のグルックのオペラ「オルフェオとエウリディーチェ」と同じだ。「オルフェオとエウリディーチェ」は、歌手の曲芸的歌唱技術を見せつけるための付随音楽に陥っていた当時のオペラを、演劇と音楽中心のオペラに引き戻すため、グルックがそのあり方を示した歴史的に重要な作品だ。音楽史ではこれをグルックのオペラ改革と呼んでいる。この改革は成功し、オペラの歴史は実際に大きく変わった。この作品によってオペラの作曲規範、評価基準は音楽の劇の内実中心になっていく。ドリーム・シアターがこのようなアウトラインを下敷きにした背景には、現在のポピュラー音楽が彼らの考える理想とは異なった方向に行っていると感じていることが挙げられる。ドリーム・シアターが考える理想については、議論の余地はあるだろう。アルバムの設定からは、技術革新がもたらす音楽への影響をドリーム・シアターが悲観的に見ていることがうかがわれ、理想のあり方に戻す「勇者」のような存在にバンド自身を投影している。自分たちが音楽の救済者なのだと。このようなメッセージは、聞く人によって反応が分かれるだろう。バンド側も、そのような反応の数々は織り込み済みとして発表しているだろう。これまでも物語性を持たせたアルバムはたくさんあったが、このアルバムは物語の鍵を音楽にしている点で他の物語とは区別するべきで、バンドのメッセージが反映されていると見なすべきだ。サウンド面では、楽器のひとつと同じようにオーケストラが参加しており、ギターやキーボードと同格でメロディーを構成する。オーケストラとバンドが対峙していた「スコア」とは異なり、5人編成のバンドが数十人に増えているようなサウンドだ。技術革新による音楽の衰退を扱い、人工的な音を再現するなら、人工的ではない伝統楽器の音としてオーケストラの音も取り入れるのは自然な成り行きだ。ポップスを中心に演奏するオーケストラを選んでいるところは、意図するサウンドに適した選択であり、クラシックの著名なオーケストラでないのはむしろ好意的に評価できる。

DISTANCE OVER TIME
2019年。9曲で57分となり、前作の半分以下。長くても9分台に収まっている。それぞれの曲が独立しているので、緊張感を長時間持続しなくても聞ける。メロディーも追いやすく、近年のアルバムでは最も分かりやすい。「フォール・イントゥ・ザ・ライト」「バーストゥール・ウォリアー」「アット・ウィッツ・エンド」は途中で一旦リセットするように間奏が始まる。演奏技術を見せつけるのは「S2N」「ペイル・ブルー・ドット」。