A WESTERN HARVEST FIELD BY MOONLIGHT
1994年。

STEREOPATHETIC SOULMANURE
1994年。1988年から1993年までの録音。カントリーやフォーク、ブルース、ロックの合間に話し声、即興演奏や雑音等が入る。日本盤は1996年発売。
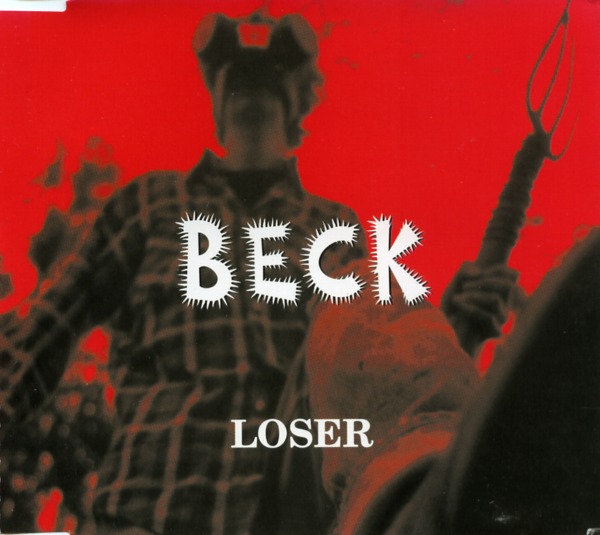
LOSER
1994年。シングル盤。アルバム未収録曲3曲収録。91年のニルヴァーナの「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」、93年のレディオヘッドの「クリープ」とともに、90年代以降のロックのあり方を規定した曲。

MELLOW GOLD
1994年。スライドギター、アコースティックギターを弾きながら、フォークとブルース、ヒップホップが混ざったようなサウンド。ベースは通常のロックよりも低音で響く。ボーカルは気だるさがあり、汗くささがない。中心楽器がアコースティックギターであるうえに、ロックとなる曲でも一般的な定型のサウンドにはならない。グランジのような筋肉質で破壊的なサウンドとは異なる別種のロックであり、その別種のイメージの総体こそがオルタナティブ・ロックだ。1990年代前半に登場したこともタイミングとして重要だ。「ペイ・ノー・マインド(スヌーザー)」はボブ・ディランのような曲。パンクのイメージはない。「ルーザー」「ビール缶」収録。このアルバムで日本デビュー。全米12位、100万枚。
ONE FOOT IN THE GRAVE
1994年。

ODELAY
1996年。フォーク、ブルースからロック中心になり、ヒップホップやクラブ・ミュージックへの接近も顕著。さまざまな録音技術をを使い、電子音とサンプリングが挟み込まれる。サウンドが常に刺激的で、ミクスチャー・ロック、オルタナティブ・ロックの代表的なアルバムのひとつになった。アコースティックギターは大きく減り、。「デヴィルズ・ヘアカット」「マイナス」はロック。「ホットワックス」「ザ・ニュー・ポリューション」「ジャック・アス」等はロックを基本として、その上にソウルやカントリー、フォークなどを載せている。「ホエア・イッツ・アット」「ハイ5(ロック・ザ・キャッツキルズ)」はヒップホップ。7曲目の最後にレコードから針を上げる音があり、8曲目の最初にレコードに針を下ろす音が入っている。レコードのA面とB面を意識したとみられる。全米16位、200万枚。
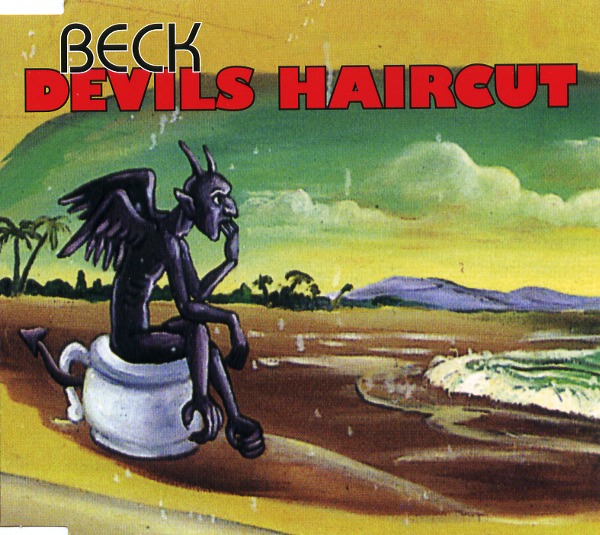
DEVILS HAIRCUT
1996年。シングル盤。

WHERE IT'S AT
1996年。シングル盤。6曲収録。「ホエア・イッツ・アット」「ロイド・プライス・エクスプレス」はダダスト・ブラザーズのメンバー、「ダーク・アンド・ラヴリー」はダスト・ブラザーズのリミックス。ダスト・ブラザーズはケミカル・ブラザーズに改名した方ではなく、もともとアメリカで活動していたデュオ。

THE NEW POLLUTION AND OTHER FAVORITES
1997年。シングル盤。8曲収録。「リチャーズ・ヘアピース」はエイフェックス・ツインのリミックス。

MUTATIONS
1998年。アコースティック・ギター、ピアノでカントリー、フォークを歌う。前作とはまったく異なり、ヒップ・ホップやクラブ・ミュージックの要素はあまり出てこない。ボーカルはメロディーがつく。60年代後半から70年代前半のシンガー・ソングライターのサウンド。音の編集やコラージュはほとんどなく、メロディーの線が自然に流れていく。シンセサイザーはすぐにアナログと分かる特徴的な音を選んでいる。時代を反映した音ではなく、「オディレイ」からのサウンド上の落差は大きい。「トロピカリア」はボサノバ風。「ダイアモンド・ボロックス」は「オディレイ」路線のハードなロック。ボーナストラックの「エレクトリック・ミュージック・アンド・サマー・ピープル」はポップでいい曲だ。全米13位、50万枚。
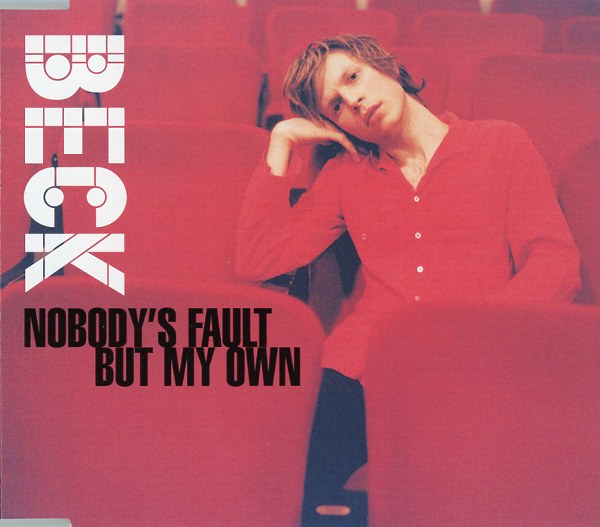
NOBODY'S FAULT BUT MY OWN
1999年。シングル盤。「ワン・オブ・ディーズ・デイズ」「ダイアモンド・イン・ザ・スリーズ」はアルバム未収録曲。60年代後半のサイケデリックなポップスの雰囲気。

MIDNITE VALTURES
1999年。「オディレイ」の路線。ホーンセクションが入り、メロディーもポップになった。ヒップ・ホップやクラブ・ミュージック、フォークのほかにソウルやファンクも加わっている。オープニング曲の「セックス・ロウズ」はイントロからホーンセクションが使われ高揚する。「ゲット・リアル・ペイド」「ハリウッド・フリークス」はヒップホップ。「ハリウッド・フリークス」と「デボラ」は「オディレイ」の時のプロデューサーが関わっているので「オディレイ」の未収録曲とみられる。多くの曲は各楽器やエレクトロニクスの音で空間を埋められている。曲の親しみやすさはこれまでで最も大きい。「セックス・ロウズ」「ミックスド・ビジネス」収録。全米34位、50万枚。

SEXX LAWS
1999年。シングル盤。ホーン・セクションやバンジョーが使われるポップな曲。キーボードはジェリーフィッシュのロジャー・ジョセフ・マニング・ジュニアが演奏している。

MIXED BIZNESS
2000年。7曲のうち5曲が「ミックスド・ビジネス」とそのバージョン違い。「サックス・ロウズ」はサックスによるインスト曲。
B SIDE COLLECTION:STRAY BLUES
2000年。シングルのB面集。

SEA CHANGE
2003年。アコースティックギターを中心とする「ミューテイションズ」に近いサウンド。「ミューテーションズ」よりも陰鬱で、曲もやや長い。アコースティック楽器にこだわらずエレキギターやエレクトロニクスも使うが、全体的な雰囲気は難しくない。現代的な音の要素を使った古風なポピュラー音楽と言える。「ペイパー・タイガー」「ロンサム・ティアーズ」「ラウンド・ザ・ベンド」は厚いストリングスが使われる。全米8位、50万枚。

GUERO
2005年。オーソドックスなロックとなり、ミクスチャー・ロックというようなイメージではない。コーラスによって曲に親しみやすさを持たせ、ヒップホップの量を減らしている。「オディレイ」や「ミッドナイト・ヴァルチャーズ」から楽器の数や曲に切り込んでくるエレクトロニクスを減らして聞きやすくした印象。「ゴー・イット・アローン」はホワイト・ストライプスのジャック・ホワイトがベースを弾く。スライドギターを使うブルース寄りの曲とエレキギターを使うロック、ポップス寄りの曲の幅が大きい。ボーカルのメロディーがポップだ。全米2位、50万枚。
GUEROLITO
2005年。「グエロ」のリミックス盤。
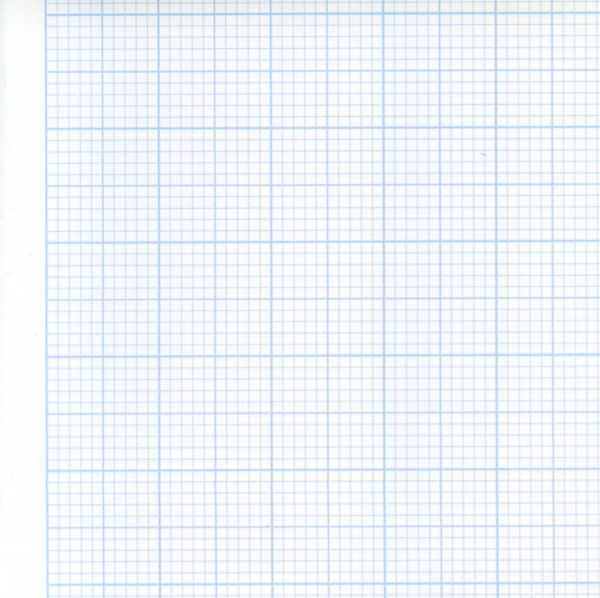
THE INFORMATION
2006年。邦題「ザ・インフォメーション」。「ジ・インフォメーション」ではない。「ミューテイションズ」「シー・チェンジ」の路線で、このアルバムを含めた3枚はレディオヘッドの「OKコンピューター」で有名なナイジェル・ゴドリッジがプロデューサーとなっている。多数のアコースティック楽器を使って細かく編集しているが、全体としては自然な流れを持った曲が多い。ロックのような熱さ、豪快さは排している。「シンク・アイム・イン・ラヴ」「ストレンジ・アパリション」聞き手に楽しさを呼ぶサウンドではないが、一部に面白みは呼ぶことができる。「セルフォンズ・デッド」「ダーク・スター」「ウィ・ダンス・アローン」はレディオヘッドに近いサウンド。「ナウジア」は多数の高音パーカッションが楽しさを増幅する。最後の「ザ・ホリブル・ファンファーレ/ランドスライド/エクソスケルトン」は3部構成で10分を超える。アルバムの後半はマッシヴ・アタックの雰囲気。全米7位。

MODERN GUILT
2008年。10曲で34分弱と分量が小さい。ドラムによるリズムが大半を占め、ギター、ベースにキーボード、ストリングス、コーラスを加えるだけの曲が続く。ボーカルにはエコーがかかり、奥行きが深い。ミドルテンポと半音階の多いメロディーがもの悲しさをつくる。「オーファンズ」「ウォールズ」は1960年代後半のサイケデリック時代のロック。「ユースレス」「レプリカ」はエレクトロニクスが活躍する。ベックはデビュー当初から自分の興味関心に基づいたロックをやっており、90年代には結果として内省的な若者が支持して成功した。どのような階層が支持するかとは別に、個人としての興味関心を追求した結果、ある程度の結果を出したと解釈できる。全米4位。

MORNING PHASE
2014年。ボーカルを含めた各楽器がほとんど加工されず、濁りなく響く。これまでで最もエレクトロニクスと音の編集が少なく、音の加工は音の立ち上がりや減衰の響きを中心になされている。刺激的な音を避けており、3世代にわたって安心して聞けるサウンドだ。ストリングスが使われる曲は重厚で、「ウェイヴ」はストリングスのみで演奏される。「サイクル」「フェイズ」は次の曲につながるストリングスのみのイントロ。アコースティックギターとボーカルの多重コーラス中心のサウンドは前作から続いている。「ハート・イズ・ア・ドラム」「ブラックバード・チェイン」はサイモン&ガーファンクルやフォークロックに通じる。「ターン・アウェイ」「カントリー・ダウン」はカントリーロックとしても優れている。全米3位。

COLORS
2017年。1980年代かというようなきらびやかなポップさがあり、ベックのアルバムとしては親しみやすい。現代的なオルタナティブロックの雰囲気を残しながら、ポップなメロディーを維持する。オープニング曲はボーカル部分の多くが2声だ。「アイム・ソー・フリー」はオルタナティブロックらしいギターが出てくる。アルバムの半数はギターよりもキーボードやシンセサイザーが主導し、白人中間層基準の軽やかなロックを響かせる。オルタナティブロックのナイーブさをいったんリセットしたか。

HYPERSPACE
2019年。11曲のうち7曲をファレル・ウィリアムスがプロデュースしている。残りの4曲はポール・エプワース、グレッグ・カースティン等がプロデュースしている。全体としてシンセサイザー中心のポップス。ヒップホップやダンスへの傾倒はあまりなく、穏やかなメロディーが多い。「ソウ・ライトニング」はファレル・ウィリアムスらしい跳ねるような音が使われており、「ケミカル」ではメロディーにファレル・ウィリアムスらしさがある。それ以外の曲では一般的なシンセサーザーポップとなっており、ファレル・ウィリアムスの柔軟性の高さが際立つ。